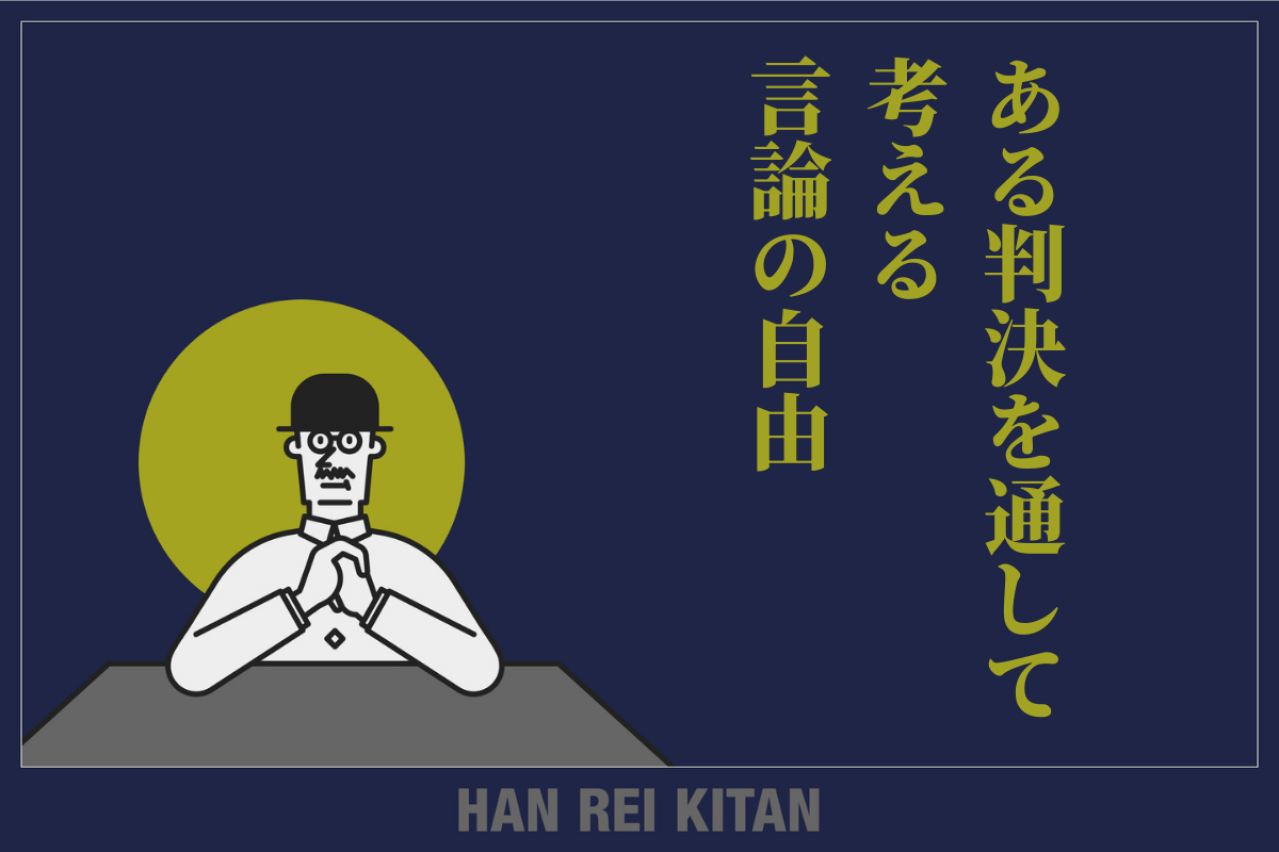
- 民事裁判
ある判決を通して考える言論の自由と責任
法廷の静寂を切り裂くように、原告Cさんの声が響きました。「裁判長!私は嘘で傷つけられました。これって、名誉毀損ですよね?」
この物語は実際の判例を元にしたフィクションです。登場人物は全て仮名にしております。実際の判例を元にした物語としてお楽しみください。
Cさんはフリーランスのジャーナリスト。
彼女は過去に、あるテレビ局の支局長Aから性被害を受けたと告発し、実名で活動を続けていました。
ある日、X(旧Twitter)で自分のことを名指しした上で、破産したという嘘の情報を拡散されたのです。加害者は被告、AI関連企業の代表取締役でした。
裁判長は静かに言いました。
「原告Cさん、あなたの主張を詳しく聞かせてください。」
Cさんは語り始めました。
「私は性被害を告発した後、漫画家Bから二次被害を受けました。Bは、私がAとの性交渉をでっち上げた、とX(旧Twitter)で発信したのです。私はBを名誉毀損で訴えました(別件名誉毀損訴訟)。そのことを知った被告は、私の訴えを批判するようなツイートを繰り返すようになり、ついに、私が破産したという全くの嘘を拡散したのです。私は破産などしていません! 私がCという名前で活動していること、性被害を告発していること、別件名誉毀損訴訟を起こしていること、これらを踏まえれば、被告のツイートが私を指しているのは明らかです。この嘘によって、私の社会的信用は大きく傷つけられ、精神的な苦痛も計り知れません。慰謝料100万円と弁護士費用10万円、合わせて110万円の賠償を求めます。」
傍聴席からは、Cさんに同情するような空気が伝わってきます。
続いて、被告が発言を求めました。
「私はCさんを破産者だと決めつけてツイートしたわけではありません。私がツイートで言及したのは別人Dです。官報にDの破産情報が掲載されていたので、それをツイートしたまでです。Cさんとは同姓同名の人物が破産したという情報がネット上に出回っていたので、Cさんのことをツイートしたと誤解されたのかもしれません。それに、『C』という名前はありふれているので、私のツイートがCさんを指すとは誰も思わないでしょう。仮にCさんのことをツイートしたとしても、官報の情報に基づいているので、真実と信じるに足る相当の理由があります。」
被告は、あくまで偶然の一致であり、悪意はなかったと主張しました。
しかし、裁判長は鋭く指摘します。
「被告、あなたはCさんが実名で活動していること、性被害を告発していること、そして別件名誉毀損訴訟を起こしていることを知っていたはずです。あなたの過去のツイートを見れば、Cさんへの敵意は明らかで、Cさんを攻撃する一環として今回のツイートをしたと判断できます。それに、あなたが使った「性行為強要」や「D」といったハッシュタグを調べると、Cさんと関連付けられることは容易に想像できます。これらの状況を考えれば、あなたのツイートがCさんを指すと考えるのが自然です。あなたは、意図的にCさんを傷つけようとしたのではないでしょうか? また、Dの破産情報がネット上で拡散されていたという証拠もありません。」
被告は言葉を詰まらせました。
裁判は進み、最終的に裁判長は判決を言い渡しました。
「被告は、原告Cさんに対し、33万円の損害賠償を支払うこと、そして問題のツイートを削除すること。原告のその他の請求は棄却する。」
傍聴席からは、安堵のため息が漏れました。
判決:原告Cさんの勝訴
原告Cさんは、被告のツイートによって名誉を毀損されたと主張し、損害賠償とツイートの削除を求めました。
裁判所は、被告のツイートがCさんを指すものであり、虚偽の情報でCさんの社会的評価を低下させたとして、名誉毀損を認めました。被告は悪意を否定しましたが、裁判所はCさんへの敵意やツイートの文脈、ハッシュタグの使用状況などから、名誉毀損の故意を認定しました。結果として、Cさんの請求は一部認められ、被告は損害賠償の支払いとツイートの削除を命じられました。
この判決は、インターネット上での言論の自由は守られるべきだが、同時に他人の権利を侵害するような発言は許されない、ということを明確に示しています。
特にSNSでは、情報が瞬時に拡散するため、一度発信した情報は取り返しがつきません。この裁判を傍聴した人々は、インターネットで発言する際には、より一層の注意が必要だと感じたことでしょう。
そして、Cさんの闘いは、インターネット社会における名誉と尊厳を守るための、一つの象徴的な出来事として記憶されることでしょう。
物語の元になった判例
判例PDF|裁判所 - Courts in Japan
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/090608_hanrei.pdf
